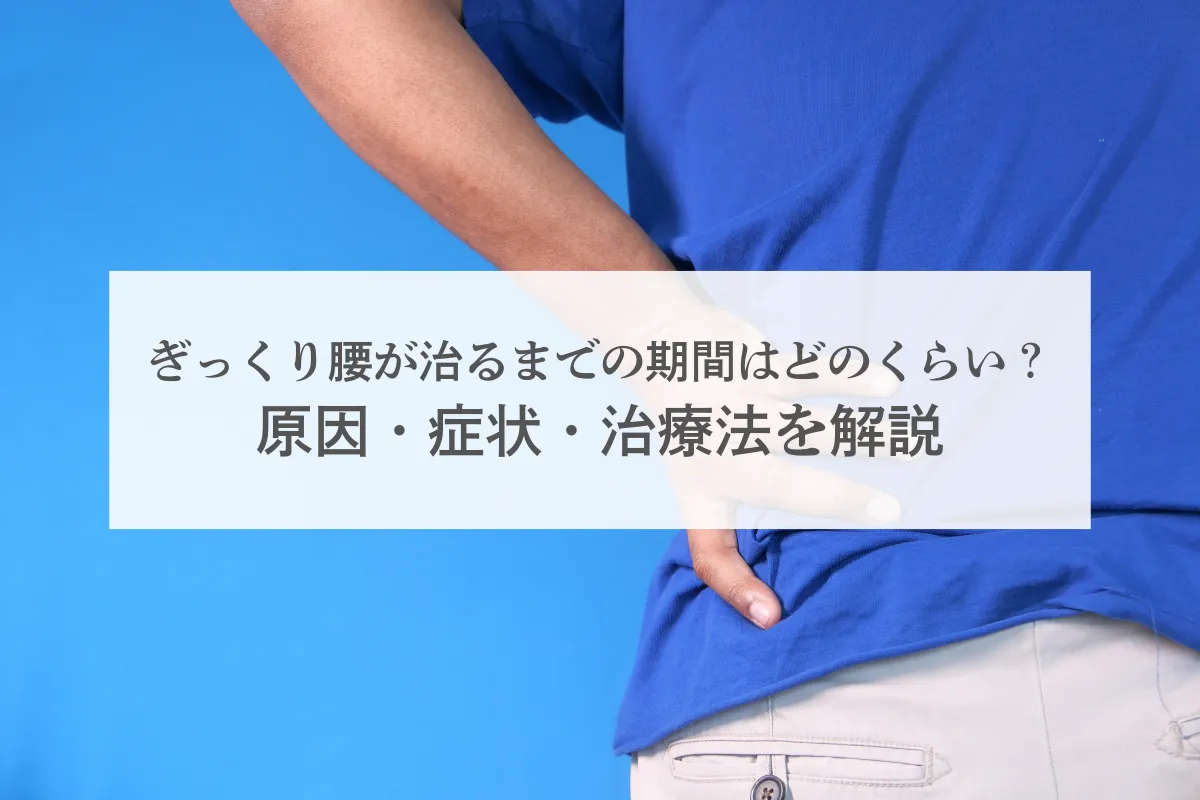
ぎっくり腰になると「どのくらいで治るのか」という期間の見通しが最大の関心事になります。急に襲ってくる激痛に驚き、不安になる方も多いでしょう。
ぎっくり腰が治るまでの期間は症状の重さによって異なり、軽度なら3日〜2週間程度、重度の場合は1〜1.5ヶ月ほどかかりますが、適切な初期対応と専門的な治療を受けることで回復を早めることができます。
このコラムでは、症状別のぎっくり腰完治までの期間に加え、原因から治療法、そして医療機関受診の判断基準までわかりやすく解説します。適切な対処で回復期間を短縮し、再発を防ぐポイントもご紹介しますので、ぎっくり腰でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
なお、当社「東京メディ・ケア移送サービス」では、ぎっくり腰で動けない方の搬送を行っています。発症直後の通院だけでなく、痛みが残っている期間の外出や通院などでもぜひご利用ください。
ぎっくり腰とは?痛みの特徴と程度による症状の違い
ぎっくり腰とは、医学的には「急性腰痛症」と呼ばれる症状で、腰に突然激しい痛みが走る状態のことを指します。「魔女の一撃」とも呼ばれるほど、予兆なく突然襲ってくることが特徴です。多くの場合、腰部の筋肉や靭帯が急激に損傷することで起こります。
ぎっくり腰は、その痛みの程度によって日常生活への影響が大きく異なります。軽度の場合は痛みを感じながらも歩行や日常動作が可能な場合もありますが、重度になると立ち上がることすらできないほどの激痛に襲われることもあります。
特に注意すべきは、一度ぎっくり腰を経験すると再発しやすくなる傾向があることです。当社ではぎっくり腰で動けなくなった方の搬送依頼を受けることも少なくありません。痛みの程度や症状の特徴を理解することが、適切な対処と回復への第一歩となります。
激痛で動けないタイプのぎっくり腰
重度のぎっくり腰は「動けないタイプ」と言われ、その名の通り身動きがとれないほどの激痛を伴います。腰痛の中でも最も辛い症状の一つです。
- 立ち上がる、座る、横になるなどの基本的な動作ができない
- 咳やくしゃみをすると激痛が走る
- 寝返りを打つことすら困難
- 腰部全体に広がる強い痛みと熱感がある
- 痛みのために呼吸が浅くなる
- トイレや入浴など日常生活の基本動作が著しく制限される
このような激痛タイプのぎっくり腰は、多くの場合、腰部の筋肉や靭帯が大きく損傷している状態です。
激痛で動けないタイプのぎっくり腰の場合、無理に動くことでさらに症状を悪化させてしまうリスクがあります。そのため、適切な姿勢でのベッドレストが必要となり、医療機関での診察が必要なケースも多いです。
歩けるけど痛いタイプのぎっくり腰
比較的軽度から中等度のぎっくり腰は、激痛には至らないものの、常に痛みを感じながら日常生活を送ることになります。
- 歩行は可能だが、痛みを感じながらの歩行となる
- 長時間の座位や立位が困難
- 前かがみになる動作で痛みが増す
- 腰を捻る動作で鋭い痛みが走る
- 痛みが片側に偏っていることがある
- 腰部の特定の箇所に痛みが集中している
このタイプのぎっくり腰は、日常生活は何とか送れるものの、仕事や家事などの活動に大きな支障をきたします。特に座ったり立ったりの動作の繰り返しや、重い物を持ち上げるような動作は避けるべきです。
痛みがあっても歩ける状態であれば、まずは整形外科や整骨院など専門医療機関での診察を受けることをお勧めします。早期の適切な治療が、回復期間の短縮と再発防止につながります。
詳しくは『ぎっくり腰で歩けるけど痛いときの対処法|仕事の可否や病院へ行くタイミングも解説』の記事もご覧ください。
ぎっくり腰の症状チェックポイント
ぎっくり腰かどうかを判断するためのチェックポイントをご紹介します。以下の症状が当てはまる場合は、ぎっくり腰の可能性が高いでしょう。
| 主な症状 | 突然の腰痛、腰部の熱感や違和感、動作制限 |
|---|---|
| 痛みの特徴 | 動作時に強まる、安静時にも持続する、局所的な痛み |
| 痛みの出方 | 前かがみ、起き上がり、腰をひねる動作で悪化 |
| 随伴症状 | 筋肉の硬直、腰部の腫れ、片側や両側の臀部への放散痛 |
| 要注意サイン | 足のしびれ、排尿・排便障害、高熱を伴う場合は別の疾患の可能性 |
実際にぎっくり腰を経験された方々からよく聞かれる表現として、「腰に電気が走った」「ぎくっと音がした気がした」「腰が抜けたような感覚」というものがあります。これらの感覚を伴う急な腰痛は、ぎっくり腰の可能性が高いです。
一方で、下肢のしびれや麻痺、排尿・排便障害などの症状を伴う場合は、ぎっくり腰ではなく、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、馬尾症候群などのより重篤な疾患の可能性があります。このような症状がある場合は、早急に医療機関を受診することが重要です。
ぎっくり腰が治るまでの期間
ぎっくり腰が完全に治るまでの期間は、症状の重さや個人の体質、治療方法などによって大きく異なります。一般的には、適切な治療と休養を行った場合、1週間から1ヶ月半程度かかると言われています。
しかし、ぎっくり腰の「治る」という状態にもいくつかの段階があります。痛みが和らぐ時期、日常生活に戻れる時期、仕事に復帰できる時期、そして完全に回復して再発リスクが低下する時期と、回復過程には段階があることを理解しておくことが大切です。
ここでは、ぎっくり腰の回復期間について詳しく解説します。
痛みの程度による回復期間の違い
ぎっくり腰の痛みの程度は人によって大きく異なり、その重症度によって回復期間も変わってきます。一般的な回復期間の目安を見てみましょう。
| 軽度のぎっくり腰 | 痛みが和らぐまで約3〜7日、完全回復まで2〜3週間程度 |
|---|---|
| 中等度のぎっくり腰 | 痛みが和らぐまで約1〜2週間、完全回復まで3〜4週間程度 |
| 重度のぎっくり腰 | 痛みが和らぐまで約2〜3週間、完全回復まで1〜1.5ヶ月程度 |
軽度のぎっくり腰は、腰に違和感や痛みはあるものの、日常生活に大きな支障がないレベルです。このような場合、適切な休養と簡単なセルフケアを行うことで、比較的短期間で回復することが多いです。
一方、重度のぎっくり腰では、立ち上がることすらできないほどの激痛を伴うため、回復までに時間がかかります。特に発症から最初の2〜3日間は痛みのピークとなり、その後徐々に痛みが和らいでいく傾向があります。
日常生活に復帰できるまでの期間
ぎっくり腰の痛みが完全に消えるまでと、日常生活に復帰できるようになるまでの期間は異なります。
| 基本的な身の回りのこと | 3〜5日程度 |
|---|---|
| 軽い家事や短時間の外出 | 1〜2週間程度 |
| デスクワークなどの軽作業 | 1〜2週間程度 |
| 肉体労働や重い荷物の運搬 | 3週間〜1ヶ月程度 |
特に最初の数日間は、無理に動こうとせず、必要最小限の動きにとどめることが重要です。痛みが強い場合、トイレや食事などの基本的な動作でさえ困難を伴うことがあります。このような状況では、家族のサポートを受けることや、必要に応じて医療機関の受診を検討しましょう。
また、日常生活に復帰する際は、一度にすべての活動を再開するのではなく、段階的に活動量を増やしていくことが大切です。最初は短時間の軽い活動から始め、痛みの様子を見ながら徐々に活動範囲を広げていきましょう。
完全回復までの期間
ぎっくり腰が完全に回復し、再発のリスクが低下するまでには、一般的に1〜1.5ヶ月程度かかると言われています。しかし、「痛みがなくなった」と感じた時点で完全に治ったわけではありません。
完全回復とは、単に痛みがなくなっただけでなく、筋力や柔軟性が回復し、正しい姿勢や動作パターンが身についた状態を指します。この状態に至るまでには、急性期~回復期と段階的なプロセスを経ることが一般的です。
| 急性期 | 発症から約1週間。強い痛みと炎症がある時期 |
|---|---|
| 回復初期 | 1〜2週間目。痛みが軽減し始め、基本的な動作が可能になる時期 |
| 回復中期 | 2〜4週間目。日常生活のほとんどが可能になるが、まだ完全ではない時期 |
| 回復後期 | 1〜1.5ヶ月。筋力トレーニングや柔軟性の向上に取り組む時期 |
特に注意すべきは、痛みが和らいだからといって油断することです。多くの方が「もう大丈夫」と思って無理をし、再発してしまうケースが少なくありません。実際、ぎっくり腰は一度経験すると再発率が高く、適切なケアを行わないと繰り返し発症するリスクがあります。
ぎっくり腰の再発を防ぐためには、完全に回復するまでの期間を十分に確保し、その間に腰回りの筋力強化やストレッチ、正しい姿勢や動作の習得に取り組むことが重要です。また、日常生活での腰への負担を減らす工夫も大切です。
ぎっくり腰の主な原因
ぎっくり腰は突然起こるように感じられますが、実際には日常生活における様々な要因が積み重なった結果として発症することが多いです。「何もしていないのに突然痛くなった」という方も多いですが、これはむしろ長期間にわたる小さな負担の蓄積が限界に達した証拠と言えます。
ぎっくり腰の予防や再発防止のためには、その原因を理解することが大切です。ここではぎっくり腰を引き起こす主な原因について詳しく解説します。
筋肉の疲労と蓄積
ぎっくり腰の最も一般的な原因の一つが、腰部周辺の筋肉の疲労や負担の蓄積です。私たちの腰は日常生活のあらゆる動作で使われているため、知らず知らずのうちに疲労が蓄積していきます。
- 長時間のデスクワークや同じ姿勢の維持
- 睡眠不足やストレスによる筋肉の緊張
- 運動不足による筋力低下
- 不適切なフォームでの運動や作業
- 栄養バランスの偏りによる筋肉の回復遅延
特に現代社会では、デスクワークが増えたことで長時間座り続ける機会が増えています。座っている状態では腰部の筋肉が常に緊張状態になるため、血流が悪くなり疲労物質が蓄積しやすくなります。また、姿勢が悪いと特定の筋肉に過度な負担がかかり、疲労の蓄積を早めてしまいます。
骨格の歪みと姿勢
骨格の歪みや不良姿勢もぎっくり腰の重要な原因となります。特に骨盤や脊椎のアライメント(配列)が崩れると、腰部に過度な負担がかかるようになります。
- 猫背や反り腰などの不良姿勢の習慣化
- 足の長さの左右差や扁平足
- 片側にばかり荷物を持つ習慣
- 足を組んで座る癖
- スマートフォンを見る際の前傾姿勢(スマホ首)
- 体の片側ばかりを使う偏った動作パターン
骨盤が歪むと、その上に乗っている脊椎も正常な配列を保てなくなり、体全体のバランスが崩れます。体はこの不均衡を補正しようと特定の筋肉に過度な負担をかけるようになり、結果として筋肉の疲労や緊張が蓄積し、ぎっくり腰のリスクが高まります。
不良姿勢は時間とともに体に「癖」として定着してしまうため、自分では気づきにくいことが多いです。定期的に姿勢をチェックし、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
突然の過負荷と急激な動き
ぎっくり腰の直接的な原因として最も分かりやすいのが、腰に対する突然の過負荷や急激な動きです。これは特に若い方や、普段から活動的な方に多く見られる原因です。
- 重い荷物を急に持ち上げる動作
- 不自然な姿勢での物の持ち上げ(腰ではなく背中で持ち上げる)
- 急な方向転換や捻り動作
- 高いところから飛び降りたときの着地の衝撃
- くしゃみや咳による突然の腰部への負荷
- 準備運動なしでの激しいスポーツ活動
特に注意が必要なのは「腰を使った持ち上げ方」です。正しいフォームでは膝を曲げて背筋をまっすぐに保ち、脚の力で持ち上げることが基本ですが、これを怠ると腰に大きな負担がかかります。
重い物を持ち上げる際は、自分の限界を知り、無理な力を入れないことが重要です。無理をせず、必要に応じて複数人で作業したり、道具を使ったりすることをお勧めします。
加齢や体質による影響
ぎっくり腰は体質や年齢によっても発症リスクが変わってきます。特に加齢に伴う体の変化は、ぎっくり腰のリスク要因となることが少なくありません。
- 加齢による変化: 筋力低下、関節の柔軟性低下、椎間板の変性、骨密度の低下
- 体型的要因: 肥満、腹部脂肪の蓄積による腰部への負担増加
- 先天的な要因: 脊椎の形状異常、脚長差、関節の過可動性
- 既往症: 過去の腰痛やぎっくり腰の経験、脊椎疾患の既往
加齢により筋肉量は自然と減少し、関節の柔軟性も低下します。50代を過ぎると、特に注意が必要です。また、椎間板は年齢とともに水分量が減少して弾力性を失い、衝撃を吸収する能力が低下します。これにより、若い頃には問題なかった動作でもぎっくり腰を引き起こしやすくなります。
肥満も腰部への負担を増加させる重要な要因です。特に腹部に脂肪が蓄積すると、腰部の前弯(腰が反った状態)が強くなり、腰椎に過度な負担がかかります。適正体重を維持することは、ぎっくり腰の予防に役立ちます。
ぎっくり腰の効果的な治療法
ぎっくり腰の治療法は、症状の段階や重症度によって異なります。適切な治療を行うことで、回復期間を短縮し、再発リスクを減らすことができます。ここでは発症直後の急性期から回復期までの効果的な治療法について詳しく解説します。
急性期(発症直後)の対処法
ぎっくり腰の急性期は、発症直後から約3日間と言われています。この時期は炎症反応が強く、最も痛みが強い時期です。まずは痛みを軽減し、炎症を抑えることに重点を置きます。
| 安静 | 安静にする(ただし長期間の絶対安静は避ける) |
|---|---|
| 冷却 | 氷や冷却材で患部を冷やす(20分程度を1日3〜4回) |
| 姿勢 | 痛みを和らげる姿勢をとる(膝を軽く曲げて横向きになるなど) |
| 薬物 | 医師の処方に従った消炎鎮痛剤の服用 |
| 動作制限 | 無理な動きを避ける(重いものを持たない、長時間座らない) |
発症直後は腰部を冷やすことで、炎症と痛みを抑える効果があります。しかし、48時間以上経過したら、徐々に温めるケアに切り替えることが推奨されています。温めることで血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。
また、急性期の姿勢も重要です。横向きに寝て、膝の間に枕やクッションを挟むと腰への負担が軽減されます。仰向けに寝る場合は、膝の下にクッションを入れて軽く曲げると良いでしょう。
回復期の治療とリハビリ方法
急性期を過ぎると、痛みは徐々に軽減し始めます。この回復期には、単に痛みを抑えるだけでなく、腰部の機能を回復させ、再発を防止するための治療が重要になります。ここからは、回復期に有効な各種治療法について詳しく見ていきましょう。
回復期の治療は一般的に以下の4つに分類されます。それぞれの治療法は単独ではなく、組み合わせて行うことで効果を高めることができます。症状や状態に合わせて、医師や理学療法士とともに最適な治療計画を立てることが大切です。
運動療法
運動療法は、ぎっくり腰の回復期において最も重要な治療法の一つです。適切な運動によって筋力を回復させ、柔軟性を高めることで、腰部の安定性を向上させます。
| ストレッチング | 腰部や臀部、ハムストリングスなどの柔軟性を高め、筋肉の緊張を緩和する |
|---|---|
| コアトレーニング | 腹筋や背筋など体幹の筋肉を強化し、脊椎の安定性を高める |
| 低強度有酸素運動 | ウォーキングや水中運動など、血液循環を促進し、全身の代謝を高める |
| 姿勢改善エクササイズ | 正しい姿勢を維持するための筋力とバランス感覚を養う |
運動療法を始める際は、痛みが出ない範囲内から徐々に強度を上げていくことが重要です。特に最初のうちは、専門家の指導のもとで行うことをお勧めします。無理な運動は症状の悪化を招く恐れがあるからです。
物理療法
物理療法は、物理的な刺激を用いて痛みの緩和や炎症の抑制、筋肉の緊張緩和などを促す治療法です。ぎっくり腰の回復期において、症状の改善を加速させる効果が期待できます。
| 温熱療法 | ホットパックや温浴、遠赤外線などで患部を温め、血行を促進して筋肉の緊張を緩和 |
|---|---|
| 電気療法 | 低周波や中周波の電流を流し、疼痛の緩和や筋肉のポンピング作用を促進 |
| 超音波療法 | 超音波のエネルギーを用いて深部組織を温め、血流を改善 |
| マッサージ療法 | 手技による筋肉の緊張緩和や血行促進 |
| 牽引療法 | 腰椎の間隔を広げ、神経への圧迫を軽減(症例によって適応は異なる) |
物理療法は多くの医療機関やリハビリ施設で提供されていますが、自宅でも一部の治療法(温熱療法など)を取り入れることは可能です。ただし、専門家の指導を受けることが望ましいでしょう。
装具療法
装具療法は、腰部を固定するためのコルセットやサポーターなどを用いる治療法です。これにより腰椎の動きを制限し、痛みの緩和と炎症の沈静化を図ります。
| メリット | ・腰部の安定性が増す ・痛みを和らげる効果がある ・日常生活での動作が楽になる ・姿勢を矯正する効果がある |
|---|---|
| 注意点 | ・長期間の使用は筋力低下を招く恐れがある ・依存性が生じる可能性がある ・サイズや固定力は個人に合わせて選ぶことが重要 ・医師や専門家の指導のもとで使用すべき |
装具療法は特に急性期から回復初期にかけて効果的です。激しい痛みがある時期や、長時間の活動が避けられない状況では、腰部への負担を軽減するために有用です。
しかし、装具に頼りすぎると本来腰を支えるべき筋肉が弱まるリスクがあるため、症状が安定してきたら徐々に装具の使用時間を減らし、筋力トレーニングに移行することが推奨されています。
薬物療法
薬物療法は、ぎっくり腰の痛みや炎症を抑制するのに効果的な治療法です。症状の程度や状態に応じて、適切な薬剤が処方されます。
| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 炎症を抑え、痛みを緩和する(内服薬、外用薬) |
|---|---|
| 筋弛緩剤 | 筋肉の緊張を和らげ、こわばりを軽減する |
| 鎮痛剤 | 強い痛みを抑制する |
| 湿布薬 | 皮膚から薬剤を浸透させ、局所的に痛みや炎症を抑える |
薬物療法は、他の治療法と併用することでより効果を発揮します。特に急性期の強い痛みがある時期には、適切な薬物療法によって痛みを抑えることで、早期の活動再開につながります。
ただし、薬には副作用のリスクも伴うため、医師の指示に従った正しい使用が重要です。特に長期間の使用や高齢者の場合は注意が必要です。症状が改善したら、徐々に薬の量を減らしていくことが一般的です。
ぎっくり腰の治療は、これらの方法を組み合わせながら、個人の症状や状態に合わせてカスタマイズすることが大切です。痛みの程度、年齢、既往歴、生活環境などによって最適な治療法は異なります。専門医による適切な診断と治療計画のもと、焦らず段階的に回復を目指しましょう。
医療機関受診の判断基準と移動方法
ぎっくり腰は症状の重さによって、自宅での安静と対処で回復する場合もあれば、専門的な医療機関の受診が必要なケースもあります。ここでは、どのような場合に医療機関を受診すべきか、そして痛みが強く動けない状態での安全な移動方法について解説します。
医療機関受診の判断基準
ぎっくり腰のすべてのケースで医療機関を受診する必要はありませんが、特定の症状や状況では専門家の診察を受けることが重要です。以下のような場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
- 激しい痛みが3日以上続く場合
- 足にしびれや麻痺、筋力低下などの症状がある
- 排尿や排便に問題が生じている
- 発熱を伴う腰痛がある
- 転倒や事故など明らかな外傷後に腰痛が発生した
- 痛みが徐々に悪化している場合
- 過去に癌の既往歴がある人の腰痛
- 高齢者の初めてのぎっくり腰
- 長期間のステロイド治療を受けている方の腰痛
特に注意が必要なのは、足のしびれや排泄障害を伴う場合です。これらの症状は、単なるぎっくり腰ではなく、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、さらには馬尾症候群などの重篤な状態を示している可能性があります。馬尾症候群は緊急手術が必要となる場合もあるため、すぐに医療機関を受診すべきです。
また、高齢者のぎっくり腰は、骨粗鬆症による圧迫骨折の可能性もあります。一見するとぎっくり腰の症状と似ていますが、適切な治療法が異なるため、専門医の診断が重要です。
痛みが強い場合の移動方法
ぎっくり腰の痛みが強く、自力での移動が困難な場合、無理な動きは症状を悪化させる恐れがあります。安全に医療機関へ移動するための方法を紹介します。
| 家族のサポート | 家族に支えてもらい、ゆっくりと動く。上半身を支える人と下半身を支える人の2人体制が理想的 |
|---|---|
| タクシーの利用 | 乗降時に注意が必要。乗車中は座席を倒すか、横になれる場合は横になる |
| 救急車の要請 | 症状が非常に重篤で、他の移動手段が取れない場合のみ検討する |
| 患者搬送サービス | 東京メディ・ケア移送サービスなどの専門業者に依頼する。痛みを最小限に抑える搬送技術を持つ |
ぎっくり腰で動けなくなった場合の移動は、何よりも「無理をしない」ことが重要です。痛みを我慢して無理に動くと、筋肉の損傷が悪化したり、回復期間が長引いたりする可能性があります。
自宅から車までの移動でさえ大きな痛みを伴う場合は、家族だけでのサポートでは不十分なことも多いです。このような場合、専門の患者搬送サービスを利用することで、安全に医療機関へ移動することができます。
当社で搬送を担当したあるケースでは、ご高齢の女性が朝起きた時にぎっくり腰になり、ベッドから起き上がることもできない状態でした。ご家族だけでは移動させることができず、当社に搬送依頼があり対応しました。専門的スタッフが痛みを最小限に抑えつつ、安全に医療機関まで搬送させていただきました。
搬送時には適切な姿勢を保つことも重要です。仰向けで膝を軽く曲げた姿勢や、横向きで膝を曲げた姿勢など、痛みを和らげる姿勢を取りながら移動することで、患者様の負担を軽減します。
東京メディ・ケア移送サービスによる医療搬送の特徴
東京メディ・ケア移送サービスでは、ぎっくり腰で動けなくなった方の医療機関への搬送を専門的に行っています。
- 専門資格を持つケアドライバーによる安全な搬送
- 車いすやストレッチャーなど、状態に応じた適切な移動補助器具の使用
- 24時間対応で急なぎっくり腰にも柔軟に対応
- 病院や施設との連携による円滑な受け入れ態勢の構築
- 医療知識を持つスタッフによる適切な対応
東京メディ・ケア移送サービスのケアドライバーは、全員が介護職員初任者研修を修了し、東京消防庁の患者等搬送乗務員適任証を取得しています。さらに、搬送に必要な基礎医学知識や搬送手法、救急法、AEDの使用法、心肺蘇生法などの認定も取得しており、万が一の事態にも対応できる態勢を整えています。
また、搬送車両も患者様の状態に合わせて選択します。座位が可能な方には介護タクシー車両、横になる必要がある重症の方には民間救急車両でお伺いします。


ぎっくり腰で動けなくなった場合、適切な医療を受けるためには安全な搬送が不可欠です。東京メディ・ケア移送サービスでは、患者様の痛みと不安を最小限に抑え、早期回復につながるようご移動をサポートさせていただきます。
まとめ
ぎっくり腰は症状の重さにより回復期間が異なり、軽度で数日〜2週間、重度で1ヶ月半程度かかります。回復を早めるには、発症直後の適切な対処(安静と冷却)と、回復期の効果的な治療(運動療法、物理療法など)が重要です。無理に動いて症状を悪化させないよう注意し、必要に応じて専門家の診察を受けましょう。
動けないほどの痛みがある場合は、東京メディ・ケア移送サービスのような専門搬送サービスの利用も検討してください。
この記事の監修者

東京メディ・ケア移送サービス代表 長井 靖
群馬県前橋市出身、臨床検査技師。
医療機器メーカーにて30年人工呼吸器の販売・保守を担当後、呼吸器搬送など医療搬送分野に特化した東京メディ・ケア移送サービスを設立。
日常のケガや病気、介護での通院のほか、輸液ポンプ、シリンジポンプなどの医療機器を導入した高度医療搬送も展開。搬送用高度医療機器の販売・レンタル、研修・セミナーも行う。
監修者・事業者について

