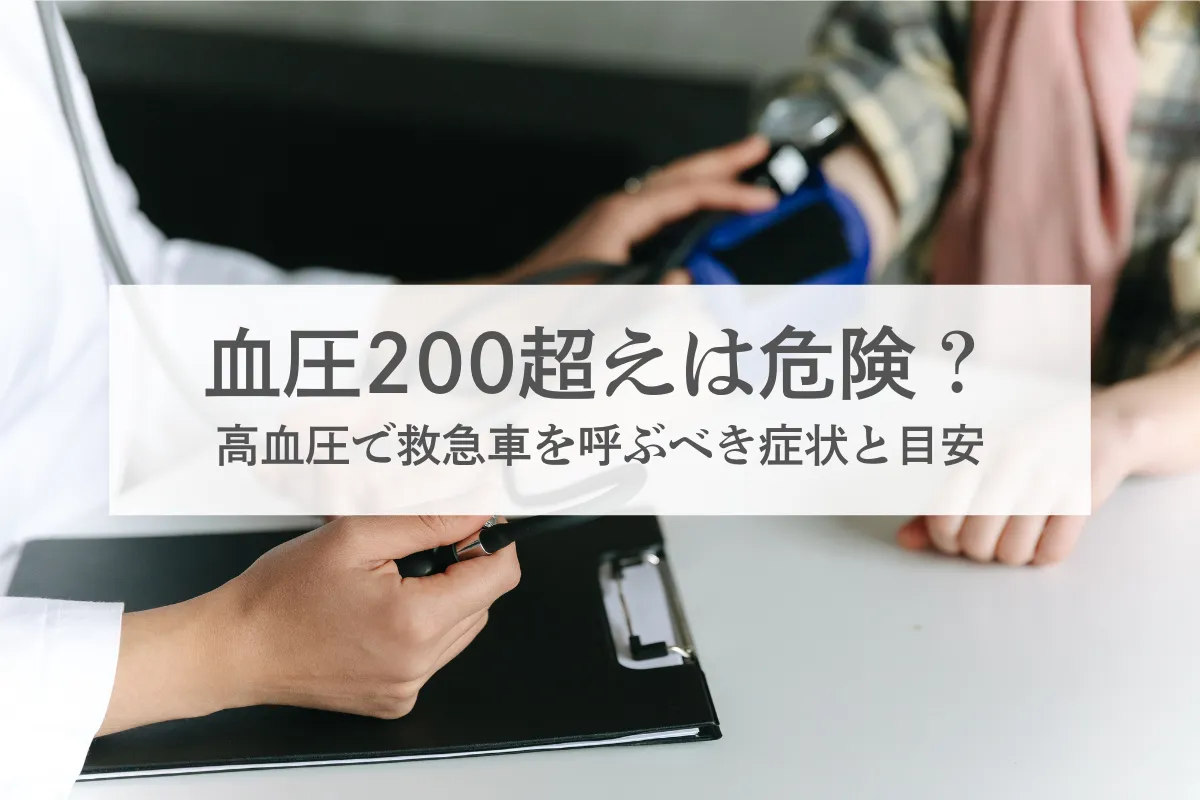
高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるほど自覚症状に乏しい病気です。しかし、血圧が急激に上昇すると命に関わる緊急事態に発展することもあります。
高血圧、すなわち血圧が180/120mmHg以上になったとき、どのような症状があれば救急車を呼ぶべきなのか、またどのような対処が必要なのかを解説します。高血圧の危険信号を見逃さず、適切な判断ができるよう、参考にしてください。
1.高血圧はいつ救急車を呼ぶべき?血圧値と症状の目安
高血圧は自覚症状がないまま進行し、ある日突然、深刻な健康問題を引き起こすことがあります。しかし、高血圧の数値が高いだけで必ずしも救急車を呼ぶ必要はあるのでしょうか?いつ救急対応が必要になるのか、明確な基準を知っておくことが大切です。
救急車を呼ぶべき血圧値の基準
救急車を呼ぶべきかの最も分かりやすい基準は血圧値です。実は日本高血圧学会のガイドラインによると、血圧値の分類は測定環境によって異なります。医療機関での測定(診察室血圧)と自宅での測定(家庭血圧)では、基準値に差があります。
一般的に、救急車を考慮すべき血圧値の目安としては、診察室血圧で収縮期血圧(上の血圧)が180mmHg以上、拡張期血圧(下の血圧)が120mmHg以上とされています。この数値は「Ⅲ度高血圧」と分類される重度の高血圧状態です。
| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |
| 正常血圧 | <120 かつ <80 | <115 かつ <75 | ||
| 正常高値血圧 | 120-129 かつ <80 | 115-124 かつ <75 | ||
| 高値血圧 | 130-139 かつ/または 80-89 | 125-134 かつ/または 75-84 | ||
| I度高血圧 | 140-159 かつ/または 90-99 | 135-144 かつ/または 85-89 | ||
| II度高血圧 | 160-179 かつ/または 100-109 | 145-159 かつ/または 90-99 | ||
| III度高血圧 | ≧180 かつ/または ≧110 | ≧160 かつ/または ≧100 | ||
| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 かつ <90 | ≧135 かつ <85 | ||
ただし、この数値に達したからといって、必ず救急車を呼ばなければならないわけではありません。血圧値だけではなく、体に現れている症状と合わせて判断することが重要です。
血圧が高いだけでなく、これらの症状があれば即救急車を

高血圧の状態で、特に以下のような症状が現れた場合は、「高血圧緊急症」という命に関わる状態になっている可能性があります。このような症状がある場合は、血圧値の高さにかかわらず、迷わず救急車を呼ぶべきです。
- 激しい頭痛(特に後頭部の痛み)
- 吐き気や嘔吐
- 視界がぼやける、視力の異常
- 手足のしびれや麻痺感
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
- めまいや強いふらつき
- 胸の痛みや圧迫感
- 呼吸困難
- 意識がもうろうとする
これらの症状は、脳卒中や心筋梗塞など、生命を脅かす緊急事態のサインかもしれません。特に、これまで経験したことのないような激しい頭痛や、突然の片側のしびれ、言葉が出にくくなるといった症状は、脳の血管に異常が生じている可能性が高いです。
血圧180/120以上で注意すべき危険信号
血圧が180/120mmHg以上の状態は、医学的に「高血圧クリーゼ」または「高血圧緊急症・切迫症」と呼ばれる状態になりつつあります。この状態では、血管に非常に強い圧力がかかっており、全身の臓器にダメージを与える危険性があります。
- 脳への危険信号:激しい頭痛、吐き気、視力障害、意識の混濁
- 心臓への危険信号:胸痛、動悸、息切れ、呼吸困難
- 腎臓への危険信号:尿量の減少、むくみの急激な悪化
血圧が180/120mmHg以上あり、こうした症状がある場合は、すぐに救急車を呼ぶべきです。たとえ症状がなくても、この数値が持続する場合は医療機関を受診してください。
2.血圧値別の危険度と対処法
血圧の数値によって、身体にかかる負担や危険性は大きく異なります。ここでは血圧値のレベル別に、どのような危険性があるのか、そしてどう対応すべきかを解説します。
血圧150〜160の場合の危険性と対応
血圧が150〜160mmHgの範囲は、日本高血圧学会の分類では「Ⅰ度高血圧」に該当します。この段階の高血圧は、すぐに命に関わる状態ではありませんが、放置すれば徐々に血管にダメージを与え、将来的に深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。
血圧が150〜160mmHgの状態が続くと、動脈硬化が進行しやすくなります。これは血管の内壁が徐々に硬くなり、弾力性を失っていく状態です。特に40代、50代、60代の方は注意が必要で、この状態を長期間放置すると、心臓病や腎臓病のリスクが高まります。
| 対応方法 | ・まずは落ち着いて再測定 ・定期的な血圧管理の開始 ・生活習慣の見直し(減塩、運動増加) ・数日以内に医療機関を受診 |
|---|---|
| 注意すべき症状 | ・頭痛や頭重感 ・疲れやすさ ・めまい ・動悸 |
この段階では、すぐに救急搬送が必要なケースは少ないですが、上記のような症状が強く現れる場合は、かかりつけ医に相談するか、休日・夜間診療所を受診することをお勧めします。また、数値が継続して高い場合は、なるべく早く医療機関を受診して、医師の指示に従うことが大切です。
血圧170〜180の場合の危険性と対応
血圧が170〜180mmHgの範囲になると、「Ⅱ度高血圧」に分類され、より注意が必要な状態です。この段階では、血管への負担がさらに増加し、心臓や脳、腎臓への影響が深刻化してきます。特に心筋梗塞や脳卒中のリスクが非常に高くなり、速やかな対応が必要になります。
| 対応方法 | ・安静にして15分後に再測定 ・症状があれば早急に医療機関へ ・症状がなくても24時間以内に受診 ・自己判断での降圧剤服用は避ける |
|---|---|
| 注意すべき症状 | ・強い頭痛 ・めまいや立ちくらみ ・視界の異常 ・胸の不快感 ・呼吸困難感 |
血圧が170〜180mmHgある状態で上記のような症状が現れている場合は、早急に医療機関を受診しましょう。特に、これまで経験したことのない強い頭痛や、胸痛がある場合は、ためらわず救急車の要請をしてください。
血圧200超えの場合の危険性と対応
血圧が200mmHgを超える状態は、「Ⅲ度高血圧」に分類される非常に危険な状態です。この段階では血管に極めて強い圧力がかかっており、脳卒中や心筋梗塞、腎不全などの重篤な合併症が急激に発症するリスクが高まります。
血圧が200mmHgを超えると、頭痛がひどくなったり、体がふわふわしたりといった症状が現れることがあります。さらに悪化すると、高血圧緊急症という重篤な状態に陥る可能性があります。
| 対応方法 | ・症状があれば直ちに救急車を要請 ・症状がなくても安静にして再測定 ・再測定でも200超えなら医療機関へ ・自力での移動は避け、搬送を考慮 |
|---|---|
| 危険な症状 | ・激しい頭痛 ・吐き気・嘔吐 ・視界の異常 ・手足のしびれや脱力 ・胸痛や呼吸困難 ・意識の混濁 |
血圧が200mmHgを超え、上記の症状がある場合は、命に関わる危険性があるため、直ちに救急車を呼んでください。これは「高血圧緊急症」という緊急事態の可能性が高く、適切な医療処置が速やかに必要です。
血圧200超えでも症状がない場合の適切な対処法
血圧が200mmHgを超えていても、特に症状がないというケースもあります。しかし、症状がないからといって安全というわけではありません。気づかないうちに臓器にダメージを与えている可能性があります。
- まず落ち着いて、5分ほど安静にした後、再度血圧を測定する
- 測定環境や体位が適切か確認する(背もたれにもたれ、リラックスした状態で測定)
- 再測定でも200mmHgを超える場合は、医療機関への受診を考える
- 自力での移動に不安がある場合は、家族に付き添ってもらうか、搬送サービスを利用する
- かかりつけ医がいる場合は、電話で相談してみる
当社で患者搬送業務を行う中で、特に気になるのは高齢者の方です。高齢者は血圧の変動が大きく、200mmHgを超えても自覚症状が乏しいことがあります。また、「病院に行くのが面倒」「家族に迷惑をかけたくない」と受診を躊躇するケースも少なくありません。しかし、この数値帯では臓器へのダメージがすでに進行している可能性があり、早期の医療介入が必要です。
東京メディ・ケア移送サービスでは、症状がなくても血圧が高い方の病院搬送に対応しています。特に高齢者や持病のある方は、安全のために専門スタッフによる搬送をご検討ください。
3.高血圧緊急症とは?命に関わる危険な状態
高血圧緊急症とは、急激に血圧が上昇し、臓器障害を引き起こしている状態のことです。単に血圧が高いだけでなく、重要な臓器に障害が生じているかどうかが診断の鍵となります。緊急の治療が必要な、命に関わる危険な状態です。
高血圧緊急症の主な症状
高血圧緊急症では、明確な症状が現れることが多いです。これらの症状が血圧上昇と共に現れた場合は、すぐに救急医療が必要です。
- 激しい頭痛(特に後頭部)
- 吐き気・嘔吐
- 視力障害・視界のぼやけ
- 意識障害・混乱
- けいれん
- 胸痛・息切れ
- 急な手足の麻痺やしびれ
高血圧緊急症で起こりうる合併症

高血圧緊急症は全身の臓器に深刻な影響を及ぼし、様々な合併症を引き起こします。特に脳、心臓、腎臓への影響が顕著で、早急な治療が必要です。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)のリスク
高血圧緊急症では脳血管に過度の圧力がかかり、脳出血や脳梗塞のリスクが急増します。脳卒中が発生すると、突然の片側麻痺、言語障害、意識障害などの症状が現れ、後遺症を残すことや、重篤な場合は命に関わることもあります。
心臓への影響(心筋梗塞・急性心不全)
過度の高血圧は心臓への負担を著しく増加させます。冠動脈の血流が阻害されると心筋梗塞を、心臓のポンプ機能が低下すると急性心不全を引き起こします。胸痛、呼吸困難、冷や汗などの症状が現れ、迅速な治療が必要です。
腎臓への影響(急性腎障害)
腎臓の血管も高血圧の影響を強く受けます。血圧が急激に上昇すると、腎臓の微小血管が損傷し、急性腎障害を引き起こすことがあります。尿量減少、むくみ、倦怠感などの症状が現れ、治療をしなければ腎機能の永続的な低下を招くことがあります。
4.高血圧を自己判断せずに医療機関を受診すべき理由
高血圧は、自分では気づきにくく、かつ放置すると深刻な合併症を引き起こす恐れがある疾患です。自己判断での対処には限界があり、病院での診断と治療が必要です。ここでは、なぜ高血圧を自己判断せず医療機関を受診すべきなのか、その理由を詳しく解説します。
自覚症状がないため
高血圧は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」と呼ばれるほど、初期段階では自覚症状がほとんどありません。多くの方が「元気だから大丈夫」と思い込み、対処を先延ばしにしてしまうのです。
高血圧は自覚症状がなくても、静かに血管を傷つけ、臓器にダメージを与え続けています。血圧が高い状態が長く続くほど、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病などの重大な疾患のリスクが高まります。
定期的な血圧測定をするため
自覚症状に乏しい高血圧を早期に発見するためには、定期的な血圧測定が不可欠です。家庭での測定と医療機関での測定を組み合わせることで、より正確な血圧の状態を把握できます。
家庭での血圧測定は朝晩の2回、できれば毎日続けることが理想的です。朝は起床後1時間以内、排尿後、朝食前、服薬前に測定し、夜は就寝前に測定します。測定値はノートに記録し、医療機関を受診する際に持参すると、適切な診断につながります。
| 測定のタイミング | 朝:起床後1時間以内、排尿後、朝食前、服薬前 夜:就寝前 |
|---|---|
| 測定の頻度 | できれば毎日(少なくとも週に3日以上) |
| 注意点 | ・測定前の30分間は喫煙、カフェイン摂取を避ける ・安静座位で5分間休憩した後に測定 ・測定値はノートに記録し、医療機関を受診する際に持参 |
年に一度の健康診断で高血圧を指摘された場合は、必ず医療機関を受診しましょう。
正しい血圧測定の方法

血圧を正確に測定するためには、適切な方法で行うことが大切です。間違った測定方法では、実際よりも高い値が出たり、低い値が出たりして、適切な判断ができなくなります。
- 椅子に深く腰掛け、背中を支え、足を組まずに床につける
- カフを巻く腕は、心臓と同じ高さになるよう、テーブルなどに置く
- カフは上腕に直接巻き、きつすぎず緩すぎない程度に調整する
- 測定中は会話せず、リラックスして安静にする
- 同じ条件で2~3回測定し、平均値を記録するとより正確
測定値が140/90mmHg(家庭血圧の場合は135/85mmHg)以上の場合は高血圧の可能性があります。ただし、一度の測定だけで判断せず、異なる日時に複数回測定して傾向を確認してみてください。そして、高血圧の可能性がある場合は、自己判断せずに病院を受診しましょう。
最近では、スマホと連携しアプリへ測定データを転送できる血圧計(NFC内蔵血圧計)もあります。測定値が自動的に記録されるため手作業の手間を省くことができ、長期的な血圧変動も簡単に確認することができます。
手首式の血圧計を利用している場合は、上腕式のものに切り替えるといいでしょう。上腕式は精度が高く、医師や日本高血圧学会も推奨する血圧計です。また、古くなった血圧計は本来の数値より高く出るなど精度に問題が生じ始めます。5年以上前に購入した血圧計を使い続けている方は、買い替えも検討しましょう。
(参考記事)血圧計は上腕式と手首式、どっちがおすすめ?特徴と選び方を解説
(参考記事)血圧計は古くなるとどうなる?古い血圧計の買い替えどきと耐用年数について
5.東京メディ・ケア移送サービスの民間救急車について
当社「東京メディ・ケア移送サービス」は、医療器具・介助器具を搭載した車両を運営する民間救急事業者です。救急車を呼ぶほどの緊急性はないが、通常のタクシーでは不安があるという方にご利用いただいています。


激しい頭痛や手足のしびれ、呼吸困難といった症状がある場合は迷わず救急車を呼びましょう。一方で、血圧は高いが現時点でそうした症状は見られない、という場合はぜひ当社の民間救急をご活用ください。
6.まとめ
高血圧は自覚症状に乏しく、そのまま放置すると重大な合併症を引き起こす危険があります。血圧が180/120mmHg以上で頭痛や吐き気、胸痛などの症状がある場合は、迷わず救急車を呼びましょう。血圧200mmHg超えは、症状がなくても医療機関への受診が必要です。
日常的な血圧測定を心がけ、高血圧と診断されたら生活習慣の改善と医師の指導を受けることが大切です。緊急性がないものの自力での移動に不安がある場合は、東京メディ・ケア移送サービスのような民間救急車の利用も検討しましょう。早期発見と適切な対応が、命を守る最大の防御策です。
この記事の監修者

東京メディ・ケア移送サービス代表 長井 靖
群馬県前橋市出身、臨床検査技師。
医療機器メーカーにて30年人工呼吸器の販売・保守を担当後、呼吸器搬送など医療搬送分野に特化した東京メディ・ケア移送サービスを設立。
日常のケガや病気、介護での通院のほか、輸液ポンプ、シリンジポンプなどの医療機器を導入した高度医療搬送も展開。搬送用高度医療機器の販売・レンタル、研修・セミナーも行う。
監修者・事業者について

